
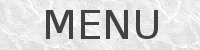
受験するにあたって
1級
重要用語
色彩文化
色彩調和論
表色系
色材
色彩管理
色彩計画
環境色彩計画
ファッションと色彩
服装史
1級オススメ参考書
2級
重要用語
ファッション用語
マーケティング用語
人名
2級オススメ参考書
3級
重要用語
ファッション
環境色彩
デザイン用語
ファッション用語
3級オススメ参考書
色彩検定講座 TOP
光と色
★光とは★
光
電磁波と呼ばれる放射エネルギーの一部です。
光は粒子としての性質と波動としての性質の両方を持っていて、色と関わりが深いのは
特に波動としての性質です。
可視光線
電磁波のうち約380nm〜780nmの間の波長です。人間の目に入り、視感覚を引き起こす
ため可視光線と言います
赤外線と紫外線
可視光線の両側には赤外線と紫外線があり、短波長側は紫外線、長波長側には赤外線
と接しています。
赤外線には熱作用があり、熱線とも呼ばれ、紫外線は化学作用や殺菌作用があり、医
療器具などの殺菌灯に利用されています
単色光
それ以上他の色光に分けられない単一波長だけの光のことです。単色光の波長ごとに
色が異なって見えます
複合光
単色光の集まりのことです
白色光
太陽の光のように色みを感じさせない光のことです。(色みをもたない複合光)
分光
白色光を波長ごとに分散させることです
スペクトル
太陽の光をプリズムに通すと分光され、虹状のの色帯が生じます。この色の配列のこと
を言います
光源
光を自ら発するもので、太陽の光などを自然光源、白熱電球などを人工光源と呼びます
光源色
光源に属しているように見える光の色です。(ネオンサインや水銀灯など)
色温度
光源の質の違いを表す尺度の一つです。完全放射体(黒体)を発した時に温度の違いが
色の違いになることを利用した表示方法です完全放射体の絶対温度は「K(ケルビン)」で
表します赤みを帯びた光は色温度が低く、青みを帯びた光は色温度が高いです。
標準の光
標準の光A・・・白熱電球(タングステン)に代表される光です。色温度は約2856Kです
標準の光C・・・北窓から入る青色の光です。色温度は約6774Kです
標準の光D65・・・紫外域を含む平均的な昼光です。色温度は約6504Kです
北空昼光
色を観察するための自然光のことです日の出3時間後から日の入り3時間前までの太陽
光の直射を避けた北窓から天空光のことです。北窓昼光とも言います。
演色性
証明光が物体色の見え方に及ぼす影響を演色と言い、光源に固有な演出についての特
性を演色性と言います
演色評価数
光源の演色性を表す指数です。数値が100に近いほど演色性が高いです
条件等色(メタメリズム)
分光分布が異なる2つの色が特定の観察条件下で等しく見えることです
同色(アイソメリズム)
分光分布が同じ2色のことですどのような光のもとで2つを見ても同じ色に見えます
★色の分類★
物体色
光を反射または透過する物体の色です
表面色
不透明な物体表面から光が反射されることによって現れる色のことです
透過色
透明または不透明な物体で、光の一部が吸収された残りが透過されることによって現れ
る色のことです
分光反射率
照明された不透明な物体から反射する光の割合を波長ごとにとらえたものです
各波長ごとの反射率を測定して結んだ線を分光反射率曲線と言います。
★目の構造★
虹彩
目に入る光量を調節するところです
水晶体
焦点距離を調節するところです
網膜
視細胞がとらえた可視光線を電気信号に変えるところです
錐体
明るいところで機能し、色覚に関わります。3種の錐体が存在することがわかっています
盲点
網膜の中心より約15度鼻側は視神経乳頭といって、網膜神経繊維の束の出口にあたり
ます。ここには視細胞がなく、光を感じることはできないのでここの部位を盲点と呼ばれ
ています
視感度
各波長の光に対して人間の視覚系がどれくらい感覚できるかという感度です。可視波長
域の明暗感覚が最大となる波長の感度を最大視感度といいます。
明所視の最大視感度は555nm、暗所視の最大視感度は507nmです
明所視
明るい昼間の状況における知覚のように桿体がほとんど機能せず、錐体によってものを
見ている状態です
暗所視
錐体がほとんど機能しないほど暗い状態での知覚のことです
プルキンエ現象
明所視から暗所視または暗所視から明所視に切り替わる中間の状態で、錐体と桿体が
両方機能している状態の視覚を薄明視と言います。
この薄明視の状態では、明るいときによく見えていた赤系の色が暗く見え、青系の色が
明るく見える現象をプルキンエ現象といいます
明暗順応
明るさの変化に合わせ、網膜上の視細胞が反応しているものを見やすくする視覚の反応
です
明順応
明るいところに目が慣れることです
暗順応
暗いところに目が慣れることです
色覚異常
一般の人のように色を見分けることができないことです